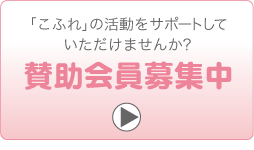離婚や面会交流に関する文献情報(その1)
「親が離婚した子どもの権利章典」
日本と米国の家庭裁判所は、一般国民に対する情報提供に大きな違いがある。
米国で離婚するためには、何らかの形で裁判所を利用しないといけないこともあってか、米国の家庭裁判所は情報提供に熱心で、法的課題だけでなく離婚が子どもに及ぼす影響などに関しても情報提供している。
離婚に関連する教育的プログラムも活発である。教育プログラムは各州ごとに工夫が見られるが、一つの例として、ニューヨーク州を取り上げてみよう。
ニューヨーク州でも離婚するためには、裁判所が認定した教育プログラムに参加することが求められている。ニューヨーク州裁判所事務総局では、離婚を考えている親用のハンドブックを刊行しており、ハンドブックは80頁ほどのもので、インターネットでも取得可能である。この中には、親が離婚した子どもの権利章典(Bill of Rights for Children Whose Parents Are Separated or Divorced)が取り上げられている。
子どもが親の離婚の影響を受ける客体としてだけでなく、権利の主体として取り上げられている点が興味深い。この権利章典では、12項目の子どもの権利が取り上げられている。いずれ日本でもこれらに関する議論が起こることを期待しながら、拙い訳文を掲げてみよう。
①両親の「どちらを選ぶか」を問われない権利。
②両親間で展開されている法的紛争の詳細を知らされない権利。
③一方の親から、他方の親のパーソナリティや人格上の「欠点」について、
説明されない権利。
④一方の親と電話で話すときに、他方の親に聞かれないプライバシーの権利。
⑤面会交流で他方の親と過ごした内容を、もう一人の親から「詳しく尋ねられない」権利。
⑥一人の親から他方の親への、伝言者となることを頼まれない権利。
⑦一人の親から他方の親へ、嘘を伝えることを頼まれない権利。
⑧元夫婦間のことに関して、相談相手を頼まれない権利。
⑨親の離婚にともなう感情を、表現する権利。
⑩親の離婚にともなう感情を、表明しないことを選ぶ権利。
⑪両親間の紛争に巻き込まれない権利。
⑫両親のどちらをも愛することに、罪悪感を感じないでおられる権利。
なお、米国では各種サービスや施設の利用者の権利を擁護するために、権利章典が老人ホームや障がい者の施設、学校などにも、掲示されていることはよくある。
(宮﨑昭夫)
離婚や面会交流に関する文献情報(その2)
面会交流に関する米国の研究の一応の結論
親が離婚後の子どもの多くは、米国でも母親と同居し、父親と面会交流を行っている。しかし、面会交流で父親と過ごす時間は、わが国とは比較にならないくらいに長い。
以下は父親との面会交流に関する研究の一応の結論であり、Alison Clarke-Stewart & Cornelia Brentano(2006). Divorce-Causes and Consequences-, Yale Univ. Press.の整理である。面会交流の頻度が少なく、1回当たりの時間が短いわが国で、米国の研究結果をそのまま用いることには問題が多いが、わが国での研究課題を示していると言えるのではなかろうか。
①面会交流が規則的に行われる場合(例えば週に1回とか、週に2回とか)に限って、
面会交流の回数の増加は子どもの福祉に結びつく。
②面会交流の期間が長い方が、子どもの自尊心や学校の成績に良い影響を及ぼす。
③子どもが面会交流を望む場合の方が、子どもに良い影響を及ぼす。
④母親が面会交流を望む場合には、子どもに良い影響を及ぼす。両親間の葛藤が強い場合は、
面会交流の頻度の増加は子どもに良い影響は及ばさず害になることがある。
⑤面会交流においては父親との接触の質が重要で、父親との情緒的な交わりが重要である。
⑥父親は、叔父さんや友人のようにではなく、親として子どもに関わることが重要である。
⑦子どもと過ごす時間の長さだけでなく、食事を作ったり、犬の散歩に行ったり、
庭の枯葉をかき集めたり、ボール投げをしたり、宿題に取り組んだり、
ベッドでの本の読み聞かせなど、日常的な交流が重要である
(楽しいことだけで過ごす、ディズニーランド・パパでないあり方)。
(宮﨑昭夫)
離婚や面会交流に関する文献情報(その3)
ジョアン・ペドロ-キャロル著、丸井妙子訳『別れてもふたりで育てる』明石書店、2015年、四六判、381頁、2,500円。
「こふれ」では従来、面会交流の援助を行ってきた子どもの年齢が幼いこともあって、スキンシップを大切にし、
穏やかで、安全で、愛情に満ちた面会交流を目指してきた。しかし、「こふれ」の活動期間が伸びるに伴い、面会する子どもの平均年齢が少しずつ上昇してきている。
2~3歳であれば、言語的表現にはかなりの限界があるが、3~4歳となり、4~5歳と成長するにつれて、子どもと的確な言語で関わり合うことの重要性が増している。さらに、スタッフが監護親や面会親へどのような言語的な働きかけを行うかも、今まで以上に課題となってきている。
離婚を子どもにどう説明したらよいかに関しては、取扱った文献も増えてきているが、面会交流時の子どもへの言語的関わり方に関しては、わが国では文献が少ない。
ペドロ-キャロルの『別れてもふたりで育てる』は、発達心理学の知見をおさえ、親が離婚した子どもの心の動きを的確に描いている。このため、離婚を子どもにどう説明するかの情報とともに、
面会交流時等の言葉かけのヒントになる情報が多いように思われる。もちろん、日本と米国では社会や文化が異なり、面会交流の態様や子どもと過ごす時間も大きく異なっており、
本書のコピーのような働きかけでは成功は難しい。本書を手がかりに、日本での工夫を重ねていくことが求められているように思われる。
本書のテーマである、米国等で行われている離婚後父母の双方が子どもの養育に関わることに関して、多くの日本人の読者にはイメージがわきにくいと思われる。
本書には、離婚後の父母が別々に養育にあたる「並行的養育」と、父母間で養育に関して協同が行われる「協調的養育」が紹介されており、参考になる点が多い。
なお、本書の訳文は全般的に読みやすいが、一部にわが国での定訳を無視した表現がある。sole legal custodyを「法的単独親権」と訳すのは許容範囲かもしれないが、joint physical custodyは「身体的共同親権」ではなく、家族法学者の棚村政行などの先行業績に従い、「共同身上監護」と訳す必要があろう(180頁~)。
(宮﨑昭夫)
離婚や面会交流に関する文献情報(その4)
紫原明子著『りこんのこども』マガジンハウス、四六判、165頁、1,300円+税、2016年。
面会交流に携わる私たちは、保育所や幼稚園就園前後の親が離婚した子どもと出会う機会が多い。私たちが出会っている子ども達が思春期を迎える頃に、親の離婚とどう向き合うだろうかということは、大変知りたい情報である。本書は、面会交流を直接取り扱っているわけではないが、私たちにとって参考になる情報が多く含まれていると思われるので、文献紹介として取り上げた。
本書の著者は離婚経験を持ち、二人の子どもを育てているシングルマザーである。「実際、子どもたちは、親の離婚をどう受け止めているのでしょうか。また、その後に続く毎日を、どんな風に過ごしているのでしょうか」(5頁)という問題意識から、離婚した家庭で育っている6世帯の子どもへのインタビューによって得た情報を再構成して、一冊の本にしたものである。
6世帯の子どもの内訳は、小学5年生女子、中学生男子(学年不明)、中1男子、高3中3の姉妹、中3女子、17歳高校男子、である。学年が高いので、自らの言葉によって表現できる年齢の子ども達の意見や態度が、本書には示されている。紙幅の都合上、個別の子どもの意見を取り上げることは出来ないが、「離婚ってさ、相手のことが嫌いになったからするんでしょ。嫌いな人の子どもの私、ママは嫌いじゃないの?」(9頁)という発言には注目したい。
「離婚の数だけ家族のドラマがある」(159頁)ので画一化できないが、「私たちはただでさえ飽きっぽく、折に触れて新しい刺激を求めずにはいられない」(160頁)存在であることを前提に論を進めている。離婚に関する大人の事情は、「ある面で離婚とは、夫と妻が健全な生活を再び取り戻すための、極めてポジティブな施策とも言えるのだ」(161頁)ととらえることが出来るとしている。しかし子どもには、子どもの事情、立場があるが、「人間の思考や感情、社会や人生といったものは、どちらかが善ならばどちらかが悪、どちらかが白ならばどちらかが黒と、決してそんな風に簡単に割り切れるものではなく、本当はもっと立体的で、多面的だということなのだ」(163~164頁)と指摘している。
「両親の不和や、別離。子どもたちが自らの抗えない境遇を通して経験したことを、その後の人生の糧に変えられる後押しをすること。きっとそれが“りこんのおとな”である私たちが“りこんのこども”である彼らに対して果たすべき大切な務めなのだろうと思うのだ」(164~165頁)と指摘している。
本書はブログやツイッターを活用する、ネットで育った世代独特の軽い文体であり、離婚を取扱った類書とはトーンを異にしているが、内容的には考えさせられるものを多く含んでいる。なお、同一著者による『家族無計画』朝日出版社、2016年、は現代家族論として秀逸。
宮﨑昭夫(NPO法人北九州おやこふれあい支援センター理事長)
[参考…………本書で取り上げられているケースの要約]
●小学5年生、女の子、実父母離婚後は母親に引き取られる。その後母親再婚。離婚後も実父との関係は、おじさん的な存在としてあったようだ。「離婚ってさ、相手が嫌いになったからするんでしょ。嫌いな人の子どもの私、ママは嫌いじゃないの?」
●中学生の男の子。2歳の時に父母離婚、母親宅で育つ。実父との交流はなく育つ。養育費は支払われておらず、母親が複数の仕事をかけもちして家計を支えた。子どもの頃には「うちにパパがきますように」と七夕の短冊に願いを書いていた。母親が再婚し、パパ(?継父)との家庭生活へ。
●中1、男の子。5歳の時に父母離婚。それ以来、父親とは会っていない。
●高3、中3の姉妹。6年前に父母離婚。離婚後も父親と子どもとの関係は続く。母親が離婚後は生活に追われ、疲れているように見えるので、「子どもとして、パパとママには離婚しないでほしかった」(103頁)との想いを持って生きている。
●中3女子。3歳の時に父母離婚し、父親出ていく。子どもは月に1~2度はパパの家に遊びに行っていた。パパに彼女が出来、再婚、子どもが出来ることになって「私がいるのに、なんでパパは別の子のパパになっちゃうんだろう」(108頁)との想いをいだく。
●17歳、高校生の男の子。2歳の時に父母離婚、父親に育てられる。母親は再婚しているが、子どもと間はLINEでのつながりはある。
離婚や面会交流に関する文献情報(その5)
ケント・ウインチェスター、ロベルト・ベイヤー著、高島聡子、藤川洋子訳
『だいじょうぶ! 親の離婚』日本評論社、2015年、133頁、1500円。
本書の原書は、親が離婚しようとする(離婚した)子ども向けの、2001年に出版された米国の本である。原著者の二人は引退した弁護士であるが、行動科学の専門家のように、子どもの心の動きを丁寧にとらえた本になっている。訳者は元(現)家裁調査官である。原書には米国人のイラストが使用されているが、訳書では日本人の漫画家によるイラストに入れ替えられている。
「この本は、親が離婚しようとしているときに子どもたちから投げかけられる、よくある質問から成り立っています。それぞれの章は、質問から始まっていますが、その答えはきっと、あなたが今抱えている疑問を解決するヒントになるでしょう。」(8~9頁)と、本書の構成に関して説明している。
具体的には、「離婚するってどういう意味?」、「離婚は、ぼく/私のせい?」、「親に会いたくなったらどうしよう?」など、22の子どもから質問に答える形で、本書を展開している。なお、本書は翻訳のため、米国と社会制度の異なる日本人の読者に対して、「子どものための解説」、「大人のための解説(その1)」、「大人のための解説(その2)」、「訳者あとがき」が付け加えられている。
本書の内容は、親の離婚にともなう子どもの感情の取扱いなど、類書と共通したこともかなり書かれている。例えば、「自分の気持ちを心の奥にしまい込むことは、決して問題の解決にはなりません。あなたがしまい込んだ気持ちは、消えてなくなってしまうことはなく、逆にあなたの心の中で暴れて、あなたをもっと苦しめてしまいます」(18頁)と記している。
原著者は、離婚のもたらす子どもにとって深刻で悲惨な側面よりも、日本語のタイトルに使われているように、「だいじょうぶ!」な側面に焦点を当てているように思われる。「あなたのお母さんとお父さんが、たとえ離婚したとしても、あなたと離婚するわけではありません。あなたの両親は、あなたに対する愛情をなくしたりはしません。いつも、そのことは忘れず覚えておいてね」(13頁)、「あなたの両親の愛情は変わらないということ、あなたにはこれからもお父さんもお母さんもいるということ。たとえ同じ場所には住んでいないとしても、あなたはこれからも両親がいて、家族がいるということ」(23~24頁)と強調している。そのような父母もいるが、離婚を契機に子どもとの関わりを無くしたり減らしたりする非同居親がいることも真実である。いわば、「子どもを捨てる非同居親」への対応策は、本書では弱い。
本書は一部翻訳に疑問を持つ点も存在するが、全体として読みやすく、参考になる点も多い。訳者は「特に小学校の高学年から中学生くらいの子どもに向けて直接書かれた本は少なく、それが、この本を訳したいと思った理由です」(120頁)と語っている。当該年齢層の子どもたちがどれくらい本書を理解し、どのように本書を評価するかをぜひ知りたいところである。
(宮﨑昭夫)
離婚や面会交流に関する文献情報(その6)
小川冨之・高橋睦子・立石直子編『離別後の親子関係を問い直す-子どもの福祉と家事実務の架け橋をめざして-』法律文化社、2016年、A5版、196頁、3,200円+税。
法律、臨床心理、児童精神医学、社会福祉政策論といった、多彩な領域の10人の著者による、Ⅲ部10章からなる面会交流を中心とした離別後の親子関係に焦点を当てた、論文集のような本である。
紙幅の都合で、部のタイトルのみを示しておこう。第Ⅰ部では「離別と親子関係、紛争と葛藤」、第Ⅱ部では「日本の子どもと家族法」、第Ⅲ部では「離別後の親子関係の理想と現実」を取り上げている。
旗幟鮮明な本であり、基本的にはフェミニズムの立場に立つ著者の主張からなる本である。行動科学の領域の論文には、新しい内容も含まれているが、法律家の書いた部分の多くは、
梶村太市・長谷川京子編『子ども中心の面会交流』日本加除出版、2015年、と主張点は変わらず、内容的に進化したとは評価できない。
例えば、「面会交流は<監護者の監護教育内容と調和する方法と形式において決定されるべき>である」(123頁)という、古式蒼然とした最高裁調査官の考え方が示されている。
評者は面会交流に関わっているが、面会交流などの離別後の親子関係がスムーズに動かない要因はケースによって異なる。
面会親側に問題のあるケースもあれば、監護親側に問題があるケースもある。しかし、本書の基本的トーンは、面会親側の問題ばかりを取り上げ、監護親側の問題を取り上げていない。
離婚後の共同養育に対するネガティブな評価を前提に、わが国における離婚後の非同居親と子どもとの面会交流に関して抑制的な主張がなされている。
初めから結論ありきで書かれている論稿が多く、論理が雑なところもかなり見受けられる。
本書では離婚に関連する家裁調査官の専門性に関して、印象記的に疑問を述べているが(例えば、111頁)、
その解決策にはふれていない。家裁調査官の専門性に関しては印象で論ずべきことではなく、エビデンス・ベースドで検討すべきことであろう。
最高裁は秘密主義的であり、調査官調査に関する組織的検討が公表される可能性は極めて低い。
このため、弁護士会などで一定数の調査報告書を収集し、組織的に調査官調査のあり方と、
調査報告書の課題を検討すべきではなかろうか。さらには、家裁調査官調査に対する、セカンド・オピニオン制度の導入の是非に関しても検討が期待される。
なお、リサ・ヤングによる10章の「オーストラリアの家族法をめぐる近年の動向」は、欧米の家族法研究者も注目している、オーストラリア家族法入門として秀逸である。本章は参考になる点が多い。
(宮﨑昭夫)
離婚や面会交流に関する文献情報(その7)
有地亨著『離婚!?』有斐閣、1987年、四六判、265頁
著者の有地先生は、家族法担当の九大教授として、また福岡家裁の家事調停委員として長年働かれ、2006年に亡くなられている。本書には判例も取り上げられてはいるが、主要な材料は、新聞の人生相談などへの一般市民からの投稿記事と、有地先生が代表として行った文部省科研費による現代家族の機能障害に関する調査研究からの情報によっている。このため主な素材は、30年前から50年前のものである。時間の経過の中で、離婚に関連する課題にはどのような変化があったのかをみるため、本書を取り上げてみよう。
この50年ほどの間の離婚に関連する主な法改正としては、①人事訴訟法の改正により、離婚訴訟が2004年より地方裁判所から家庭裁判所へ移管された、②民法第766条が改正され、養育費及び面会交流が法律の本文に登場し、2012年より実施された。③家事審判法が家事事件手続法に改正され、2013年より裁判所の手続に変更がみられた。しかし諸外国のように、ドラステッィクな家族法の改正は行われず、限られた部分的な改正が行われた。
わが国の離婚率は、本書が出版された1987年は1.30であり、その後徐々に増加したが2002年の2.30をピークに減少し、2015年には1.81となって、本書が出版された時期よりも、離婚率はやや高止まりしている。離婚の種別では、協議離婚が約9割、調停離婚が約1割で、裁判離婚は少数という傾向は、最近でも大きくは変わっていない。「これまで長い間、離婚には悲劇的なイメージがつきまとい、離婚は人生における失敗・挫折というマイナスのイメージで受け取られてきた。(中略)このような考え方に多少の変化が現れ、離婚は人生の転機または一つのステップとプラスのイメージでとらえるようになった人びとも出てきた」(149頁)、との見方は現代でも通用するであろう。
本書で取り上げられている、離婚に関連する「夫の暴力」などの課題は、現代でも通用する。本書で取り上げられている、財産分与や慰謝料などの金額は、伸びが低迷しているように思われる。養育費に関しては、厚生省の1968年調査によると「夫のほうで養育費を負担しているのは僅か10%」(179頁)と記している。2011年の国の調査によると養育費を受け取っている人は約2割であり、受給者率は伸びてはいるが低迷しており、養育費をめぐる課題に関しては、大きな変化はない。
面会交流(本書では時代を反映して「面接交渉」と表現してある)を支援する「こふれ」のような第三者機関が存在しない時代に本書は出版されているが、面会交流を積極的に位置付けている。著者の、「面接交渉の成功の秘訣は、子どもは両方の親の家を往き来しても、親は相手の家に行かないし、親はお互いに相手の悪口を絶対に言わないこと、(中略)そしてなによりも子どもを引き取った母親は、子どもに対してつらいけれども、どうしても離婚しなければならなかった事情について、事実を正確に伝えて、時間をかけて話し合うことがまず必要である」(223頁)、との指摘は現代でも生きているように思われる。
本書には、調停委員の基本的姿勢や態度に関する厳しい指摘も含まれており(208頁など)、裁判所関係者などに今日でも参考になる点が含まれている。ともあれ温故知新として、時間のある時に手に取って読んでみてほしい書籍である。本書はかなり古い本のため、書店での購入は無理であり、公共の図書館等での閲覧をお勧めしたい。
(宮﨑昭夫)
離婚や面会交流に関する文献情報(その8)
善積京子『離別と共同養育-スウエーデンの養育訴訟にみる子どもの最善-』世界思想社、2013年、A5版、3,500円+税
福祉国家スウエーデンにおける、離婚(別)とその後の共同養育はどう行われているか本格的に紹介した文献である。本書は裁判例を中心としているが、スウエーデンにおける親子法の変遷や制度的解説も含まれている。1970年以降に限っても、スウエーデンでは親子法を10回改正し(38~39頁)おり、時代の状況にあわせて家族法を頻繁に変えていることが示されている。
父母(カップル)が不仲になると、共同養育を行うか否か、居所(子どもがどこに住むか)や面会(交流)をどうするかが課題となる。この紛争を取扱うのはスウエーデンでは地方裁判所であるが、ソーシャルワーカーが働く社会福祉サービス機関である、家族法事務所と連携して対応している。家族法事務所では、協調的対話(調停と同義の活動と思われる)、調査、コンタクトパーソン(面会交流時の付添人)の斡旋などを行っている(50頁)。
著者は、2004・2005年のストックホルムとイエーテボリの、地方裁判所における離別後の子どもの養育に関連した事件(1293件)のデータを収集している。そのうち詳細な係争経過記述のある「事例ケース」(131件)を分析対象として論稿を進めている。
スウエーデンでは「共同養育が子どもにとって最善という考え方を前提にして成り立っている」(157頁)。「両方の親が共同養育に反対する場合を除いて、共同養育に反する特別な事情あるときのみ、子どもの養育権は両親のうちの一方の親に任される」(157頁)。
「親子法において子どもは別居親と面会する権利を持つと明記され」(102頁)、「<面会は親の権利>から<子どもの権利>へと根本的な転換がなされた」(25頁)。子どもと親との面会交流が危険だと判断された場合には、コンタクトパーソン付の面会交流が裁判所によって定められたりしている。DVに関連して、「暴力行為が<過去の出来事>や<一過性の出来事>であり、現在被害者への影響は<ない>、あるいは<少ない>と判断される場合には、たとえ有罪判決が下されていても、それによって親が<養育者として不適格>とされたケースはなかった」(99頁)と記している。
スウエーデン研究に基づいて、今後のわが国の改革の方向性として、著者は主に以下の指摘を行っている。①わが国も共同親権、共同監護に向けた法改正を行うべきである。②面会交流がスムーズにいくように、公的な面会交流の場の提供と、コンタクトパーソンを付ける公的支援体制の整備。③家裁調査官制度を改革し、養育問題に関する調査機構の充実。④「両親との親密な交流が子どもの基本的ニーズである」(201頁)という意識を社会全体に広げる啓発活動を行う。
著者は、追手門学院大学社会学部の教授である。本書は、大阪市立大学に提出された学位論文を再構成して出版したものである。法律家の書いた本とはかなりトーンを異にしており、参考になることも多い。
(宮﨑昭夫)
離婚や面会交流に関する文献情報(その9)
二宮周平編『面会交流支援の方法と課題-別居・離婚後の親子へのサポートを目指して-』法律文化社、A5版、230頁、2017年、3,200円+税
本書は、立命館大学の二宮教授が科研費を活用して行った「家事事件当事者の合意による解決と家事調停・メディエーション機能の検証」と題する研究の一部として刊行されたものである。中心は2015年11月29日に京都で開催された、全国の主だった面会交流支援団体が参加して行われた、「面会交流支援団体フォーラム2015」での報告である。なお、このフォーラムには「こふれ」からも参加している。
フォーラムで示された、各団体の面会交流支援上の工夫には目をみはるものがあり、「こふれ」にとっても参考になる点が多い。活動の幅としても、単なる面会交流支援にとどまらず、子ども達への学習支援活動、遠足、離婚家庭の子どもたちを集めたキャンプや合宿、利用者を対象にした「母親達の集い」「父親たちの集い」のような利用者の父母に対するセミナーなどもある。面会交流支援活動のプロセスとしては、事前相談の工夫や面会終了後の当事者やスタッフ間での振り返りの方法などにも参考になる点が多い。さらに、スタッフの増員養成のための支援者養成講座などからも学べる点が多い。
本書にはフォーラムで報告しなかった団体を含めて、編者が選択した団体が、編者の指定した面会交流に関するテーマで論稿を提出しており、これらも参考になる。面会交流を行っている団体は、元家裁調査官、家事調停委員などの司法関係者、臨床心理士関係者、保育関係者、宗教関係者など多様である。その中にあってピアサポート(同様な境遇にある仲間からの支援、この場合は親の離婚を経験した子どもとしての経験を有する人)を中心とする団体である、ウイーズの活動も紹介されており、示唆に富む提言が含まれている(171~188頁)。ウイーズは静岡市・浜松市より委託を受けて、面会交流仲介支援も行っている。
本領域の先進自治体である、明石市の幅広い活動も紹介されている(189~201頁)。末尾の資料欄には、Vi-Projectによる「離れて暮らす親子のためのハンドブック」、養育支援制度研究会による「子どものためのハンドブック」なども収載されている。
本書には幅広い主張と内容が含まれており、面会交流での立ち位置によって、多様な読み方が可能だと思われる。評者としては、本書を読むことによって、初心に帰ることの大切さを教えてもらった思いである。本書を手がかりに、「こふれ」の実務をていねいに見直していきたいと切望している。
(宮﨑昭夫)
離婚や面会交流に関する文献情報(その10)
ジュディス・ウオラースタイン他著、早野依子訳『それでも僕らは生きていく-離婚・親の愛を失った25年間の軌跡-』PHP、四六判、450頁、2001年
なお、翻訳の原書は2000年刊
やや古い本ではあるが、国際的に著名な本であり、このところ面会交流慎重派から引用されることの多い本なので取り上げてみよう(例、渡辺義弘「心理学的知見の教条化を排した実務運用はどうあるべきか」梶村太市、長谷川京子編『子ども中心の面会交流』。可児康則「司法における面会交流の現実」小川冨之他編『離別後の親子関係を問い直す』など)。本書はアマゾンなどで、古本としてなら購入可能。
著者の故ウオラースタイン(1921~2012年)は、離婚の当事者や、離婚に巻き込まれた子どもの抱える課題を研究した、世界を代表する研究者といっても過言ではない。米国の名門州立大学、カリフォルニア大学バークレー校の社会福祉学部の教授を長年にわたり務めた。彼女は親の離婚を経験した子どもが、時間経過の中でどのような成長・発達上の課題に向き合ってきたかを明らかにする研究を行った。彼女の著書で日本語に翻訳されているのは、本書と高橋早苗訳の『セカンドチャンス』草思社、である。翻訳が出版されていない離婚関連の本が数冊ある。
本書では、①夫婦の不和にともない、親が離婚した場合と、不和にも関わらず離婚をしなかった場合の、子どもの成長の比較、②家庭内暴力(DV)がありながらも離婚した場合と、離婚しなかった場合の子どもの成長の比較、などが取り上げられている。
著者らの研究は、1971年にカリフォルニア州マリンカウンティで別居・離婚の申立があった60家族131人の子どもを対象に始まり、18か月後、5年後、10年後、15年後、25年後の動きを考察したものである。本書では親の離婚・別居から25年後の状態に中心をおき、「離婚が完全な大人になった後の若者たちの人生形成にどう影響を及ぼすか」(15頁)を分析したものである。このため本書で取り上げられている「子ども」は、一番年下でも20代後半であり、年長の者は40代前半になっている。
本書の結論の一つは「離婚は長期に及ぶ危機であり、何年にもわたって心理面に影響を及ぼすのだということがわかってきた」(37頁)。「これまでの私たちの認識に反して、離婚の最大の衝撃は子供時代や思春期に訪れるのではなく、むしろ、異性との恋愛が中心になる成人期に頭をもたげてくるのだ」(38頁)と指摘し、「離婚は一時的な危機であり、大人が立ち直れば子供も完全に回復するという」(427頁)のは神話だと指摘している。
裁判所に対しては、「面会や監護権の計画を立てるとき、子供の友人関係や遊びに(中略)法廷に至ってはまったく無頓着だ。一般的な台本では、主役は親なのだ。舞台の中央を占めるのは、親のスケジュールや希望や権利である。私は何百という法廷判決に目を通し、何千回も親たちと話をしたが、子供の友人関係や遊びを維持することの大切さについての言及はほとんどなかった」(71頁)と指摘している。さらに、「裁判所が子供の利益を第一に考えているとはとても信じがたい。むしろ、裁判所には何も見えていないのだ」(281頁)。「なぜ法制度は、子供は変わっていくという事実、あるいは子供が自分の生活を決める計画に参加する権利をもつべきだという事実を把握していないのだろう。十二歳の子供が、六歳のときにぴったりだった靴を履くように命じられたらどうするだろう?」(282頁)。「私の研究で、裁判所の命令や調停による両親間の取り決めによって生活を牛耳られていた子供たちは揃って、自分のことを、仲間が当たり前のように享受している自由を奪われた下級市民のように感じたと語っている」(278頁)、「子供たちを守る、あるいはせめてこれ以上子供たちの心の傷を深めないための新しい解決策が切実に求められている。法制度は行き詰っている」(281頁)、という指摘は今日の日本には無縁なことであろうか。
面会交流に関しては、「面会のスケジュールは、双方の親の要求に見合う形で組まれていた。八歳と十三歳になっていた子供たちの希望や要求は、何一つ考慮されなかった」(270頁)。「六歳の子供のためにつくられた面会スケジュールが、十三歳の子供の要求に見合って当然だと思われている。子供が新しい成長段階に達するたびに、その意見を取り入れながら柔軟な対応をしていくことがどうしてできないのだろう?」(279頁)、と司法の非柔軟性を糾弾しているが、わが国ではどうであろうか。親子関係に関しては、「私の研究で、離婚後も双方の両親と親密な関係を維持した子供はひと握りしかいない。親子関係の変遷は、親や裁判所の予想を遥かに超えたものなのだ」(437頁)とウオーラースタインは指摘しているが、日本ではどうなのだろうか?実証的研究が待たれるところである。
全般的に本書は読みやすい訳文ではあるが、一部には正確でない訳文が含まれている。一か所だけ例示すると「精神分析の専門家」(268頁)の原文はmental health professionalsであり、直訳すれば「精神保健の専門家」ないし「精神衛生の専門家」であり、米国的文脈では、精神科医、臨床心理士、ソーシャルワーカーを意味する言葉である。
本書から何を学ぶかに関しては、多様な判断があろう。評者としては著者が、①親の離婚は子どもに長期的で深刻な影響を及ぼしうることを指摘し、②離婚を取り巻く当時の米国の裁判(調停を含む)制度に対し、柔軟性に欠け問題解決に効果的でないことを指摘していることに注目したい。評者にとっては、著者の指摘は決して過去のことではなく、現在の日本においても継続している課題であると思われる。
(宮﨑昭夫)
離婚や面会交流に関する文献情報(その11)
宮﨑保成著『面会交流原則的否定論への疑問-親子引き離し弁護士への反論集-』∞books(ムゲンブックス)、B6判、55頁、2016年、1,058円。
なお本書はアマゾンのオンデマンド本である。
本書には著者の紹介部分がないので、インターネット情報で補足しておこう。著者は臨床心理士で、裁判所での面会交流紛争の当事者のようである。このため、本書には面会交流に関連した生々しい記述がかなり含まれている。
本書は『法律時報』2260号(平成27年8月11日号)に掲載された、梶村太市、長谷川京子、渡辺義弘の3人の弁護士の論文に対する、反論集である。3人の論文は「面会交流の原則実施を疑問視する弁護士たちは、面会交流が子どもに好ましくないのは例外的な事案で あるのに、それを一般化してしまうことで誤った結論に至っているように思える」(2頁)と考え、3本の論文に対し個別に反論を書くとともに、三者に共通すると思われる問題点を記したものである。
著者は梶村の論文に対して、17点にわたって検討を加えている。長谷川の論文に対しては、25点にわたって検討を加えている。渡辺の論文に対しては、4点にわたって検討を加えている。紙幅の都合で、これらの論点のすべてに評者としてコメントすることは出来ないので、代表的論者である梶村に関して3点コメントしてみよう。
①梶村は家裁の調停で面会交流の合意をしても、その44%が実施されていないことに関して、実施率を上げる工夫を考えるのではなく、「梶村太市氏は、調停で面会交流を合意しても 実施される確率が低いのだから、調停で面会交流の合意をすべきではないと述べているのだ」(4頁)と、梶村の転倒した論理を指摘している。
②梶村は「十数年前に締結した<子どもの権利条約>を今更のごとく持ち出して原則的実施論を根拠づけようとしても、全く説得力がない」(7頁)と述べている。これに対し著者は、「梶村太市氏は、条約の効力が時の経過とともに低減するとでも言いたいのだろうか」(7頁)と指摘している。評者もかねがね梶村が子どもの権利条約の理念を軽視し、本条約を実務に生かす工夫を求めてこなかったあり方に疑問を抱いていたため、著者の指摘を肯定したい。
③梶村は日本を含む「東アジアの価値観を挙げ、共同親権化・共同監護化には限界があると述べている」(8頁)こ とに対し、著者は「東アジア諸国の親権や面会交流の状況について比較検討しているわけではないのだから、そもそも論じるに値しない」(8頁)と指摘している。念のために評者は梶村の論文にあたってみたが、注等で東アジア諸国の価値観に関する新しいデータは示されておらず、エビデンスではなく、梶村の個人的信念が書かれていることが分かった。
梶村は今までも面会交流に慎重な主張をしており、主張に一貫性がみられるのは良い点かもしれないが、内容的に進化のない同様な主張を、タイトルだけ変えて種々の本や法律雑誌に掲載するやり方は、評者には納得がいかない。
なお本欄で評者は、通常の学術出版物と同様に、人名は敬称略で記している。
(宮﨑昭夫)
離婚や面会交流に関する文献情報(その12)
西牟田靖著『わが子に会えない-離婚後に漂流する父親たち-』PHP、四六判、318頁、2017年、1650円+税。
著者はノンフィクション作家である。著者自身の離婚後子どもに会えない経験が出発点となって、離婚後にわが子に会えない父親の生活を取材して、18組のケースをノンフィクション的に取り上げた本である。「子どもに会えなくなった男たちとはいったいどのような人なのか。別れに至るまでにどのように出会い、子どもをつくり、そして別れたのか。そして別れた後、どんなことを思い、どのような人生を歩んでいるのか。善悪では計りきれない多くの人生、つまりはより多くの視座伝えることで“会えない”という現象に可能な限り接近したいと思っている」(6頁 )とプロローグでは語っている。
本書は父親側の言い分だけを取り上げており、離婚になった理由なり離婚の経緯に関して、母親側の言い分を取り入れると見えてくる図もかなり異なったものとなる可能性はある。父親側の言い分だけを聞いているせいか、別れた(元)妻の言動に関して否定的な発言が多い。しかし一部の登場人物は、内罰的に結婚生活に関して父親(夫)としての足りなさや不適切さに焦点をあて、結婚生活を振り返っている点にも着目したい。
18人のケースはまさに多様であり、浮気相手と登山に行き、山から滑落して浮気がバレ、養育費や面会交流に関して、何も決める余裕もなく離婚したケース。今までに3度の結婚をし、2度離婚しながら、すでに3度目の妻とも別居状態になっており、 それぞれの妻との間に子どもがいるケース。家事をまったくやらず、子育てに興味を持たない女性との結婚生活のケース。外国(中国)人との結婚生活のケース、などが含まれている。
離婚の手続としては、一般的な協議離婚の他に、公正証書を利用したケース、裁判所の調停を利用したケース、最高裁まで争ったケース等、多様である。本書では、弁護士が妻側に介在してDVとして取り上げられたケースの比率はかなり高い。それに、妻が子どもを実家等に連れ去り、別居を既成事実化しているケースもかなりあった。
「自分の例は特殊だと思っていたのが、皆同じようなパターン(虚偽DV、悪徳弁護士、親が黒幕、等々)で苦労していること」(28頁)という表現にあるように、本書に登場する人物の主張に よれば、弁護士の活動に振り回されているケースの占める割合は高く、「弁護士による離婚ビジネスの存在」(99頁)を問題視している。
「司法の世話になることで、問題の解決を“邪魔”されたり、人によっては“とどめ”を刺されたり。司法によって不幸がもたらされたと言えなくもないケースがまれではなく、裁判所が親子を引き裂いた、と言ってしまっても、言いすぎではなかった」(315頁)と、著者は主張しているが、この主張は一般化できることであろうか。
(宮﨑昭夫)